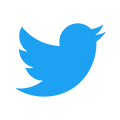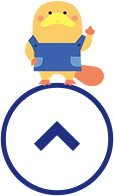発表会シーズンに向けて!子どもの表現活動を支えるポイント

秋から冬にかけて、保育園や幼稚園ではいよいよ「発表会」の準備が始まります。
劇や合奏、ダンス、歌…子どもたちが日ごろの成果を発揮する姿は、保護者の方々も楽しみにしている大きな行事のひとつですよね。
でも、発表会と聞くと、「子どもたちがうまくできるか心配…」「練習中、どんな声かけをしたらいいの?」と悩んでしまう保育学生さんもいるかもしれません。
そんな時に知っておくと安心なのが、子どもの表現活動を支えるちょっとしたポイントです。
今回は、これから就職して発表会に関わる場面や実習期間中でも困らないよう、実践に役立つポイントをわかりやすくご紹介します!
そもそも表現活動とは?
まず、発表会で行う表現活動とは、子どもたちが感じたことや思いを、体や声、表情を通して表すことを指します。
具体的には、
・歌をうたう
・音楽に合わせて体を動かす
・劇で登場人物になりきる
・絵や製作で表現する
といった活動が含まれます。どれも、子どもたちにとって「自分を出す」「みんなと一緒に楽しむ」大切な体験です。
発表会は、こうした表現活動の集大成といえますが、「上手に見せること」が目的ではありません。
大切なのは、子どもたちが楽しみながら表現することです。
保育学生として関わる際も、この視点を忘れずにサポートすることがポイントになります。
練習の中で大切にしたいこと
・「できること」より「楽しめること」を大切に
発表会の練習では、どうしても「うまくできるか」「覚えられるか」に目がいきがちです。
でも、子どもたちの中には恥ずかしがり屋さんもいれば、元気いっぱい表現する子もいます。
それぞれのペースを大切にしながら、「やってみたい!」という気持ちを引き出す関わりが大切です。
できる、できないではなく「楽しいからやってみよう」という気持ちを育てることが、表現活動の第一歩。
就職先で発表会に関わるときも、この視点を忘れずに関わることで、子どもが安心して表現できる環境を作れます。
・小さな成功体験を積み重ねよう
子どもは「できた!」という感覚を通して自信を育てます。
練習の中で少しでも上手にできた場面があったら、すかさず褒めてあげましょう。
「すてきな声だったね!」
「今の動き、とってもかっこよかったよ!」
などと、行動を具体的に褒めることで、子どもは「自分の表現が認められた」と感じ、自信を持って次に取り組めるようになります。
・子どもの思いを聞くことも大切に
練習の中で「やりたくない」「恥ずかしい」という気持ちが出る子もいます。
そんなときに無理にやらせるのではなく、気持ちを受け止めることが大切です。
「緊張しちゃうんだね」
「見ているだけでもいいよ。やりたくなったら教えてね」
と伝えることで、子どもは安心感を持ち、自然と自分のタイミングで参加できるようになります。
発表会はみんなで作る時間なので、子どもの心の準備も大切にしたいですね。
保育学生としての関わり方
保育実習の時期と発表会の準備期間が重なることもあります。
そんなとき、学生としてどんな姿勢で関わればいいのか、いくつかポイントを紹介します!
・子どもの様子をよく観察する
どの子が楽しそうにしているか、どの子が少し戸惑っているか、表情や体の動きをよく見てみましょう。
子どもの変化に気づけることは、実習生として大切な視点です。
・練習のサポートでは“支える役”に徹する
大道具の準備や並び順のサポートなど、裏方の仕事もとても重要です。
「子どもたちが安心して表現できる環境を作る」という気持ちで関わると、先生方からも信頼されます。
・子どもの気持ちに寄り添う声かけを
「緊張するね」「でも大丈夫、先生たちが見てるよ」といった共感の言葉が、子どもにとって大きな支えになります。
特に発表会当日、ドキドキしている子には、やさしい一言が心に強く響きますよ。
学生としてここを意識するだけでも、子どもが安心して活動できる環境作りに貢献できます。
まとめ
発表会シーズンに向けて、子どもの表現活動を支えるポイントについてお話ししてきました。
発表会は、子どもたちの成長を感じられる特別な行事です。
でも、その裏には緊張と向き合いながら、一歩ずつ頑張る子どもたちの姿があります。
保育学生さんにできることは、完璧な指導ではありません。
一人ひとりの表現を温かく見守り、支えることが大切。
「上手にできたかどうか」よりも、「どんな気持ちで取り組んでいたか」に目を向ける視点を持つことで、子どもたちのやる気や自信を引き出せます。
この考え方は、実習だけでなく、就職後も発表会や表現活動に関わる際に役立つ視点です。
子どもたちと一緒に楽しみながら学び、成長を支える経験として活かしていきましょう!