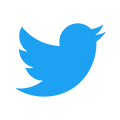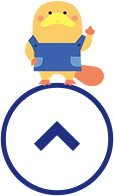七五三を保育にどう取り入れる?子どもに伝えたい日本の伝統行事

11月になると、神社の境内で着物を着た子どもたちとご家族の姿をよく見かけますよね。
この時期は、日本の伝統行事「七五三(しちごさん)」の季節です。
七五三は、子どもの成長を祝い、これからの健やかな成長を願う大切な行事。
近年では、神社にお参りするだけでなく、写真館で記念撮影をする家庭も増えています。
保育園や幼稚園でも、この行事にちなんだ活動を取り入れることがあります。
「子どもたちにどう伝えたらいいんだろう?」「実習で七五三をテーマにした活動はできるかな?」と悩む保育学生さんも多いのではないでしょうか。
今回は七五三の基本的な意味、子どもにわかりやすく伝える工夫、保育現場での活動アイデアをご紹介していきます!
七五三ってどんな行事?
七五三は、子どもの健やかな成長をお祝いする日本の伝統行事です。
古くは平安時代から行われており、当時は「3歳で髪を伸ばし始める」「5歳で袴を着る」「7歳で帯を使い始める」といった節目の儀式がありました。
現代では、11月15日前後に3歳・5歳・7歳の子どもが晴れ着を着て神社にお参りし、これまでの成長を感謝し、これからの健康を願う行事として親しまれています。
園児たちにとってはまだ少し難しい内容かもしれませんが、
「大きくなったことを神様にありがとうする日」
「これからも元気に過ごせますようにとお願いする日」
と、やさしい言葉で伝えると理解しやすくなりますよ。
七五三を子どもたちにどう伝える?
子どもたちに「七五三」をわかりやすく伝えるには、いろいろな形で“感じられる体験”を取り入れるのがおすすめです。
・絵本や写真で雰囲気を感じる
行事を伝えるときは、絵本や写真など目で見てわかる教材が効果的です。
七五三のお参りの様子や千歳飴を持つ姿を見せることで、子どもたちも行事の雰囲気をつかみやすくなります。
たとえば、絵本『七五三ってなあに?』(ポプラ社)や『きょうは七五三』(偕成社)を読み聞かせしたあとに、
「みんなも3歳や5歳のときにお祝いしてもらったかな?」
「どんなお菓子をもらったか覚えてる?」
と話を広げていくと、子どもたちが自分の経験とつなげやすくなります。
・ 千歳飴の意味を楽しく伝える
七五三といえば「千歳飴(ちとせあめ)」ですね。
千歳飴は「長いあめのように、いつまでも元気で長生きできますように」という願いが込められています。
保育では、実際に本物を見せたり、折り紙や画用紙で千歳飴袋を製作する活動もおすすめです。
袋に好きな模様や絵を描き、「中には何のあめを入れようかな?」と話しながら楽しむことで、自然と行事の意味も伝わることでしょう。
・ 遊びやごっこを通して体験する
3〜5歳児クラスでは、七五三ごっこも人気です。
画用紙で冠や帯を作って着物風に変身したり、神社を模したスペースでお参りごっこをしたりと、遊びながら行事を感じられる体験になります。
「神様、ありがとう」「これからも元気に遊べますように」と手を合わせる姿はとてもかわいらしく、ごっこ遊びの中で“感謝する気持ち”や“お祝いする楽しさ”を自然に感じ取ることができます。
・ 製作活動で表現する
七五三をテーマにした製作は、年齢に合わせていろいろ工夫できます。
例えば…
【0・1歳児】手形スタンプで成長の記録カードを作る
【2歳児】折り紙で千歳飴や着物を作る
【3〜5歳児】着物姿の自画像製作
などがおすすめです。
実習中に提案する場合は、短時間でできる簡単な製作や、既存の活動にプラスできる内容を選ぶと良いでしょう。
実習で七五三を取り入れるときのポイント
保育実習の中で七五三をテーマにした活動を行うときは、行事の意味を伝えることよりも、行事を通して子どもと一緒に季節を感じることを意識してみましょう。
例えば、お散歩中に神社を見つけたら「もうすぐ七五三だね」と話してみたり、絵本の読み聞かせを通してお祝いする気持ちを共有するのも良いですね。
子どもが「着物かわいい!」と言ったら、その気持ちを受け止めて一緒に楽しむのも大切です。
行事の知識を教えるよりも、子どもの反応を大切に寄り添う姿勢が、実習では特に求められます。
まとめ
今回は、保育学生さんに向けて、七五三の意味や子どもたちにわかりやすく伝える工夫、実際の保育活動のアイデアをご紹介しました。
七五三は、日本の伝統を感じながら、子どもの成長をお祝いするあたたかい行事です。
保育の中で取り入れるときは、難しい説明をするよりも、ありがとうの気持ちや元気に大きくなった喜びを子どもたちと一緒に感じることを大切にしてみましょう。
絵本を読んだり、千歳飴袋を作ったり、七五三ごっこをしたり…伝統行事を楽しく伝えるチャンスは身近なところにたくさんあります。
実習や授業の中でも、「どうしたら子どもたちが楽しめるかな?」と考えながら関わることで、きっと保育の楽しさをさらに感じられるはずです。