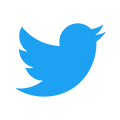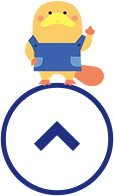ICT化が進む保育現場。先生や保護者にどんな変化が?

ここ数年で、私たちの生活はぐんとデジタル化が進みました。
スケジュール管理や授業の連絡、提出物のやり取りも、スマホやアプリを使うのが当たり前になっていますよね。
このような変化は、保育現場にも少しずつ広がってきています。
連絡帳や写真販売なども、今ではアプリや専用のサービスを通じて行う園が増えているのです。
「ICT化」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、実際には保護者や保育者、そして子どもたちにとっても身近で便利な変化を生んでいます。
そこで今回は、連絡帳アプリや写真販売などのICT化がどのように保育を変えているのかをお教えしていきます!
ICT化で保育はどのように変わった?
・連絡帳アプリが広げるつながり
かつての連絡帳といえば、保育者が子どもの1日の様子をびっしり手書きでまとめ、保護者は家に帰ってから読んで返信を書くというスタイルが一般的でした。
手書きのやり取りには温かみがありますが、時間も手間もかかるのが正直なところです。
最近は、スマートフォンやタブレットで使える連絡帳アプリが広がっています。
保育者がアプリに入力するだけで、食事や睡眠、体調などの情報がリアルタイムで保護者に届きます。
さらに、文字だけでなく写真や動画も一緒に送れるため、園での様子がより伝わりやすくなりました。
例えば、「今日は絵の具遊びをしました」という報告に、活動中の写真を添えることで、保護者は子どもの表情や楽しむ様子を感じ取ることができます。
また、発熱や体調不良などの緊急連絡もアプリで素早く行えるため、子どもの安全を守る手段としても有効です。
・写真販売の変化
もうひとつ大きく変わったのが、写真販売の仕組みです。
以前は、現像した写真を廊下に掲示し、保護者がチェックして注文する方法が一般的でした。
しかしこれでは、忙しくて見に行けない家庭も多く、申し込みも手間がかかりました。
いまでは、インターネット上の専用サイトから写真を閲覧・購入できるサービスが主流に。
スマホで簡単に見られるため、保護者も仕事の合間や家でのリラックスタイムにもチェックでき、「この写真かわいいね」と家庭での会話のきっかけにもなっています。
保育者にとっても、印刷や掲示、注文集計といった手間が減り、その分子どもと関わる時間に集中できるようになりました。
・おたよりのデジタル化
以前は、園だよりやクラスだよりを保育者が手書きで作り、印刷して配るのが一般的でした。
現在は、パソコンで作成したおたよりをアプリで配信する園が増えています。
おたより作成は、子どもと直接関わらない時間で行うことが多いため、デジタル化によって事務作業の効率化が進み、保育者の負担軽減につながっています。
保護者もスマホで手軽に確認できるため、「紙をなくした」「見るタイミングを逃した」といった心配も減りました。
・保育者の働き方も変わる
ICT化は、保護者や子どもだけでなく、保育者の働き方にも変化をもたらしています。
保育者は日々、子どもの様子を細かく観察し、記録を残すことが大切な仕事の一つです。
以前は手書きでの記録が中心で、時間がかかり残業につながることもありました。
アプリを活用すれば入力が簡単で、データも自動で整理されるため、記録にかかる時間が短縮され、保育そのものに向き合う時間を増やすことができます。
こうした効率化は、保育の質を高め、働きやすい環境づくりにもつながっています。
ICT化で気をつけたいこと
一方で、ICT化には注意すべき点もあります。
・データの管理やセキュリティ
子どもの写真や個人情報はとても大切なものなので、安全に扱える仕組みを整える必要があります。
たとえば、写真販売や園での様子を共有する際に、「どこまでの範囲を保護者が見られるようにするか」など、ルールをしっかり決めておくことが大切です。
・保護者との“顔の見える”関係を大切に
ICT化で便利な反面、保護者との直接的なコミュニケーションの場が減ってしまうという懸念もあります。
アプリ上のやり取りだけに頼らず、送迎のときのちょっとした会話や、行事での交流など、人と人とのつながりを大切にすることも忘れないようにしたいですね。
まとめ
ICT化による保育の変化についてお話ししてきました。
保育の現場にICTが導入されることで、連絡帳アプリや写真販売など、多くの場面で便利さや安心感が広がっています。
保護者にとっては子どもの園での姿をリアルタイムで知ることができ、保育者にとっては業務の負担が軽くなるという良い点があります。
子どもにとっても、家庭と園がより近い関係で成長を支えてくれるという環境が整いつつあります。
もちろん、デジタルの力だけに頼るのではなく、人と人とのつながりを大切にしていく姿勢は欠かせません。
ICT化は、あくまで保育を支える道具のひとつです。
道具をうまく活かしながら、子どもにとってより良い環境をつくっていくことが、これからの保育に求められる姿だといえるでしょう。