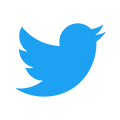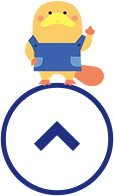子どもとの距離がぐっと近づく!声かけフレーズ集

保育の現場では、子ども一人ひとりと信頼関係を築くことがとても大切です。
信頼関係があるからこそ、子どもは安心して自己を表現し、さまざまな経験に挑戦できます。
そのためには、日々の何気ない声掛けが大きな役割を果たします。
声掛けは単なる言葉ではなく、子どもを理解し、受け止めようとする保育者の姿勢を表す行為です。
今回は「子どもとの距離を縮める声掛け」の具体例をご紹介し、それぞれの言葉が持つ意味や効果について、わかりやすくお伝えしていきます!
子どもと距離を縮める声掛けとは?
・「見てたよ」「気づいたよ」
子どもの行動に気づいていることを伝える言葉です。
大人に見守られていると感じることで、子どもは安心し、自分の存在が認められていると実感できます。
「〇〇していたね」「頑張ってたね」と言葉を添えると、子どもの自己肯定感をより育むことができます。
・「先生にも教えてくれる?」
子どもが発見したことや取り組んでいることに関心を示し、学びの主体者として尊重する声掛けです。
保育者が「知らないふり」をするのではなく、本当に知りたいという気持ちで尋ねることが大切です。
この問いかけは、子どもの「伝えたい」「分かち合いたい」という気持ちを引き出し、対話を深めるきっかけになります。
・「どうしたの?何か困ったことあった?」
困っている表情や泣いている姿を見たときに、すぐに解決策を提示するのではなく、まず気持ちを受け止めるための言葉です。
「どうしたの?」と優しく尋ねることで、子どもは安心して気持ちを表現できます。
感情を共有することは、信頼関係を築く第一歩です。
子どもが自ら気持ちを言葉にできるよう、寄り添う姿勢を大切にしましょう。
・「やってみたい?」
新しい遊びや活動に誘うときに有効な声掛けです。
無理に勧めるのではなく、子どもの「やってみたい」という気持ち、主体性を尊重する姿勢が伝わります。
「やってみたい?」と聞かれることで、子どもは自分で選ぶことができるので、自分で選び、活動することでやる気や達成感にもつながります。
・「ありがとう」
子どもの行動や思いやりに対して、感謝を伝える言葉です。
「片付けてくれてありがとう」「貸してくれてありがとう」といった言葉は、子どもの行為を肯定的に受け止めるだけでなく、感謝の気持ちを学ぶきっかけにもなります。
大人からの「ありがとう」は、子どもの自尊感情を高める魔法の言葉です。
・「いいね」「すてきだね」
肯定的な言葉は、子どもの自己表現を広げる力になります。
ただし、表面的な褒め言葉で終わらせず、「〇〇の色を選んだのがすてきだね」と具体的に伝えることが大切です。
具体的な言葉掛けは、子どもの努力や工夫に光を当て、自分らしさに自信を持たせます。
・「一緒にやろう」
子どもが挑戦しようとしていることに寄り添う姿勢を伝えられる言葉です。
「一人では難しい」と感じている子どもにとって、「一緒にやろう」という言葉は大きな安心につながります。
共に取り組む経験は、信頼関係を深めると同時に、友達や先生と一緒に取り組むことの楽しさを学ぶ機会にもなります。
・「待ってるよ」
子どもがなかなか踏み出せないときに有効な言葉です。
「早くして!」ではなく「待ってるよ」と伝えることで、子どもは自分のペースを尊重されていると感じます。
安心して自分のタイミングで行動できる環境を整えることは、主体性を育て、信頼関係を築くうえで欠かせません。
まとめ
ここまで「子どもとの距離を縮める声掛け」についてお話ししてきました。
子どもとの距離を縮める声掛けは、単に関係を良くするためのテクニックではありません。
子どもを尊重し、その存在や思いを受け止める保育者の姿勢そのものです。
「見てたよ」「ありがとう」といった日々の小さな言葉の積み重ねが、子どもに「大切にされている」という感覚をもたらし、安心して自分を表現できる心の土台になります。
また、保育者がどのような言葉を選び、どんな気持ちで伝えるかは、子どもの自己肯定感や社会性の育ちにも大きく影響します。
何気ない声掛けの中にこそ、子どもとの信頼関係を築く鍵があるのです。
日々の保育の中で、一つひとつの言葉を大切にしていきたいですね。