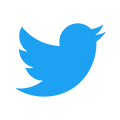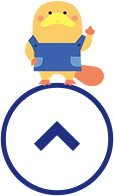自分でやってみたい気持ちを育てる見守る保育とは

保育園や幼稚園で子どもと関わっていると、「手伝ってあげたい」「教えてあげたい」と思う場面はたくさんあります。
靴を履くのに時間がかかっているとき、食事がなかなか進まないとき、友達とおもちゃを取り合っているときなど、大人が介入すればすぐに解決できることも、子どもにとっては「学びのチャンス」になることがあります。
そこで大切にされているのが、見守る保育です。
見守る保育とは、単に放っておくのではなく、安心できる環境を整えたうえで「子どもが自分でできる機会を大事にする」ことに重きを置いているのです。
今回は「見守る保育とはどういう保育なのか」をわかりやすくお教えしていきます!
見守る保育とは?
「見守る保育」とは、子どもが自分の力で考え、選び、挑戦する姿を信じ、保育者がそっと寄り添いながら、必要なときだけ援助する関わり方のことです。
・見守る保育における保育者の役割
見守る保育では、保育者は「ただ見ている人」ではありません。
子ども一人ひとりの姿をしっかり観察し、困ったときにすぐに援助できるよう準備しておくことが大切です。
そのためには、子どもの発達段階や性格を理解し、どんな援助が必要なのかを常に考える力が求められます。
また、保護者との共有も大切です。
時には「先生はなぜ手伝わないの?」と感じられることもあるかもしれません。
そこで「今日は自分で靴を履けました」「友達と話し合って順番を決められました」と具体的に伝えることで、保護者も子どもの成長を実感し、安心して見守る姿勢を受け止められるようになります。
保育生活の中における「見守る保育」とは?
見守る保育は、子どもたちの生活や遊びのあらゆる場面で実践できます。
・遊びの場面
砂場で山を作っている子どもが、「もっと大きくしたい!」と夢中になっているとします。
保育者がすぐに「お砂に水を足すと固まって、崩れずに高い山ができるよ」とアドバイスすれば確かに立派な山は作れます。
しかし、見守る保育ではあえて言葉をぐっと飲み込みます。
そうすることで、子どもが失敗したり、友達に相談したりしながら自分で試行錯誤する時間を大切にできます。
やがて自分なりの工夫を見つけたり、友達と協力して完成させたりする経験は、大きな達成感や仲間意識につながっていきます。
・食事の場面
スプーンをうまく持てず、食事がこぼれてしまう子どももいます。
大人が食べさせればすぐに食事は終わりますが、それでは「自分で食べられた」という実感が持てません。
見守る保育では、多少こぼしても自分で食べる経験を優先します。
その代わり、テーブルクロスを敷いて汚れても片付けやすくしたり、食器を持ちやすい形にしたりと環境を工夫します。
これにより、子どもは「できた!」という喜びを味わい、自分で食べる力を少しずつ身につけていきます。
・生活の場面
着替えや靴の脱ぎ履きでも同じことが言えます。
時間がかかるからと大人が急いで手を貸してしまうと、子どもの「自分でやってみたい」という気持ちが弱まってしまいます。
見守る保育では、必要なときにだけ声をかけたり、袖を少し整えて「ここを引っ張ってごらん」とヒントを出したりします。
保育者は横で見守りながら、子どもができたときには「できたね!」と認めることで、子どもは次の挑戦への自信を得るのです。
・友達との関わり
おもちゃの取り合いなどトラブルの場面では、つい大人が「順番ね」「仲良く使おうね」と仲裁したくなりますよね。
しかし見守る保育では、まず子ども同士がどう解決するのかを待ちます。
「貸して」「いやだ」というやり取りの中で、子どもは言葉で気持ちを伝える練習をします。
必要があれば保育者が「どうしたいのかな?」と気持ちを代弁し、解決に向かうよう支えます。
子ども同士のやり取りを尊重することで、相手を理解し、折り合いをつける力が自然に育っていきます。
まとめ
見守る保育についてお話ししてきました。
見守る保育は、子どもが自分の力を信じて挑戦し、失敗しながら学んでいく姿を尊重する保育のあり方です。
遊び、食事、着替え、友達との関わりなど日常の中で「自分でやってみる」経験を大事にすることで、子どもは達成感や自信を得て、仲間と生きていく力を育んでいきます。
保育者にとっては「介入するタイミングを見極める」ことが求められるので、決して簡単なことではありません。
子どもを信じて一歩引いて待つことができるよう、保育者も日々の保育での関わり方を考えていけると良いですね。