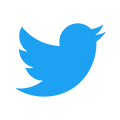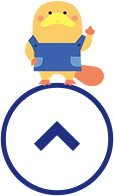静かにしている=いい子?おとなしい子の気持ちを見逃さない

保育の現場では、元気いっぱいに動き回る子や大きな声を出す子に比べ、静かに過ごしている子は「手がかからない」「落ち着いていていい子」と思われがちです。
けれども、静かにしているからといって、心の中まで落ち着いているとは限らず、実は不安や緊張を抱えていたり、自分の気持ちをうまく言葉にできずにいるのかもしれません。
大切なのは、「静かにしている=安心している」と決めつけず、一人ひとりが発している小さなサインに気づき、その気持ちに寄り添うこと。
今回は、保育における「おとなしい子」への理解と、心に寄り添うための関わり方について考えていきます。
静かにしている=「いい子」ではない
日本の保育や教育の文化の中では、長い間「静かに座って先生の話を聞くこと」「集団に迷惑をかけないこと」が“良い子”の条件とされてきました。
けれども、静かにしている子どもにはそれぞれの理由があり、中にはSOSのサインである場合もあることを忘れてはいけません。
・大人の期待に応えようとしていることも
大人に「すごいね」「えらいね」と思われたい気持ちから、声をひそめたり自己主張を抑えたりする子もいます。
その姿は外から見ると「とてもいい子」ですが、実は「怒られたくない」「嫌われたくない」という不安や緊張が隠れていることもあります。
・おとなしい子の心の内は?
静かに過ごす子どもたちをよく観察すると、それぞれ少しずつ違いが見えてきます。
信頼できる大人や安心できる環境の中で、穏やかに遊びや生活を楽しんでいる子
新しい環境に慣れず、声を出したり行動したりすることに戸惑っている子
思いを言葉にすることが苦手で、結果的におとなしい印象になってしまう子
こうした背景を持つ子どもたちに対して、保育者は「静かさ」だけで判断せず、表情や視線、体の動き、遊びへの関わり方などから、心の状態を丁寧に読み取る姿勢を大切にしたいですね。
おとなしい子の気持ちを見逃さないためには?
・観察を深める
静かにしている子どもは、一見安心しているように見えても、実は不安で動けない場合があります。
表情や体の向き、視線などに注目し、「どんな気持ちで静かにしているのか」を見極めましょう。
日々の小さな変化をメモしておくことが、子どもの心を理解する手がかりになります。
・小さな声や行動を受け止める
おとなしい子が出した小さな声や仕草を丁寧に拾い上げることは、「自分の思いが届いた」という経験につながります。
これは自己肯定感を育むうえで欠かせない大切な体験です。集団の中で目立つ子に気を取られがちですが、同じようにおとなしい子にも意識して目を配りましょう。
・安心できる関係を築く
静かな子どもほど、信頼できる特定の保育者の存在が安心の拠り所になります。
「この先生が見てくれている」という実感があると、少しずつ自己表現へ踏み出すことができます。
日常の中で継続的に「あなたを大切に思っているよ」と伝え続けることが大切です。
・多様な表現方法を用意する
言葉だけに頼らず、絵・音楽・身体表現など、多様な方法で気持ちを伝えられる環境を整えましょう。
小さなことでも自分なりに表現できると、「できた!」という自信につながります。
その子に合った方法を一緒に探してあげることがポイントです。
・集団での雰囲気に配慮する
「大きな声で発表できる子がえらい」といった価値観が支配すると、おとなしい子はますます声を出しにくくなります。
いろいろな表現の仕方が尊重されるクラスの雰囲気をつくることで、子ども一人ひとりが安心して自分を出せるようになります。
まとめ
保育の場において、静かにしている子を「手がかからないいい子」と一面的に評価することは危険です。
おとなしい子どもの中には、安心して穏やかに過ごしている子もいれば、不安や緊張を抱えている子もいます。
だからこそ保育者は、外から見える静かさにとらわれず、子どもの小さなサインを丁寧に受け止める姿勢が求められます。
そして、安心できる関係性や多様な表現の機会を用意することで、子どもは少しずつ自分らしさを発揮できるようになります。
子どもが心から安心して「自分の思いを伝えたい」と思える環境を、一緒に育んでいきましょう。