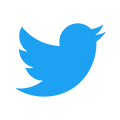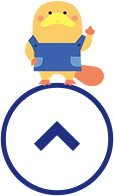特徴的な保育を知ろう!自分に合う保育を見つけるヒント

子どもたちの心と体の成長を支える「保育」は、国や地域によって考え方や取り組み方が大きく異なります。
日本はもちろん、世界各国でも、それぞれの文化や歴史、教育観に基づいた“その国ならでは”の保育スタイルが育まれてきました。
今回は、日本と海外の代表的な保育法について、わかりやすくご紹介します。
いろいろな保育のかたちを知ることで、自分に合った保育のヒントが見つかるかもしれませんよ!
日本の特徴的な保育法
日本では、子どもの心と体の発達をバランスよく支えるために、さまざまな工夫が凝らされた保育法が取り入れられています。
ここでは、日本で広く知られる特徴的な保育法の一例をご紹介します。
・はだし保育
はだし保育は、子どもたちが園内の室内や園庭を中心に裸足で過ごす保育法です。
足の裏から刺激を受けることで、運動機能や免疫力、バランス感覚の発達を促します。
土踏まずの形成や、風邪をひきにくい身体づくりにもつながるとされており、自然とのふれあいや感覚面の発達にも効果があるといわれています。
ただし、安全面に配慮して、床や園庭の清掃を徹底するなどの工夫も必要です。
・安田式運動遊び(安田式体育遊び)
跳び箱、鉄棒、巧技台(こうぎだい)などを使って、楽しく体を動かしながら、挑戦心や自己肯定感を育てる運動遊びです。
転んだり、うまくいかない経験も成長の一部と捉え、「やってみる力」を大切にしています。
小さな「できた!」という成功体験を積み重ねることで、自信や意欲へとつなげていくことができます。
・ヨコミネ式教育法
運動、読み・書き・計算の学習をバランスよく行い、子どもの競争心や自立心を引き出すことを目的とした教育法です。
園では、逆立ちやかけっこ、跳び箱などを取り入れた運動活動に加え、読書や百ます計算、暗唱などの活動も行われています。
できた喜びや負けたくない気持ちを通して、自ら伸びようとする力を育てるのが特徴です。
・森のようちえん
自然環境の中でのびのびと遊びながら学ぶ保育です。
北欧の自然保育をルーツとし、四季を感じながら遊びや活動を展開します。
雨の日も外で活動するなど、自然とのふれあいを日常に取り入れることで、創造力や社会性、そして自分で考えて行動する力を育みます。
“生きる力”を育てる保育として、日本でも注目が高まっています。
世界の特徴的な保育法
世界各国には、子どもの発達を促すためにさまざまなアプローチが存在します。
ここでは、代表的な保育法をいくつかご紹介します。
・レッジョ・エミリア・アプローチ
イタリア発祥の保育方法で、「子どもは100の言葉(表現手段)を持っている」という考え方が特徴です。
絵画や工作、音楽など多様な表現活動を通して、子どもの表現力や思考力を育みます。
教師は子どもの行動を観察し、記録することで学びの過程を見える化し、保護者と共有することも大切にしています。
・モンテッソーリ教育
イタリア発祥で、世界中に広がっている教育法です。
子どもが自ら主体的に学べる環境づくりを重視しており、日本でもモンテッソーリ教育を取り入れる園が増えています。
異年齢保育や専用の教具を使った個別活動が大きな特徴です。
・シュタイナー教育
ドイツ発祥の保育法で、芸術活動や自然とのふれあいを重視します。
テレビやデジタル機器を避け、感性や創造力の育成に力を入れています。
日々の生活リズムや季節の行事を大切にし、遊びは模倣から自由な創作へと発展させていきます。
・フォレスト・スクール
北欧発祥の保育スタイルで、自然の中で自由に遊びながら学ぶことを目的としています。
子どもたちは森や野外で過ごし、自然環境のリスクを体験しながら判断力や協調性、身体能力を育てます。
自然素材を使った創造的な遊びを中心に、五感や観察力、共感性を高めることも特徴です。
・テファリキ
ニュージーランド発祥の比較的新しい保育法で、名前はマオリ語で「織物の敷物」を意味します。
これは、子ども一人ひとりの学びが文化や価値観、経験、人間関係という「糸」によって織りなされるという考えを象徴しています。
集団行動を強制せず、一人ひとりの気持ちを尊重しながら自由遊びを中心に進め、「自ら考えて行動する力」を育みます。
多様な文化や言語、価値観を持つ子どもたちが互いに学び合い成長する姿を「織物」に例えた教育観で、現代の多様性を尊重する考え方のひとつです。
まとめ
日本と世界の保育法を比較してみると、共通しているのは「子ども自身が育つ力」を信じ、その力を引き出す環境づくりを大切にしている点です。
どの保育法にも、「子どもは未熟で守るべき存在」という考えと同時に、「子どもは自ら育つ力を持っている」という信頼が根底にあることがわかるのではないでしょうか。
保育に「これが正解」という答えはありませんが、子どもの発達段階や個性、そして地域の環境に合わせて、柔軟に保育の方法を取り入れていくことが、より良い保育につながることを忘れずにいたいですね。